
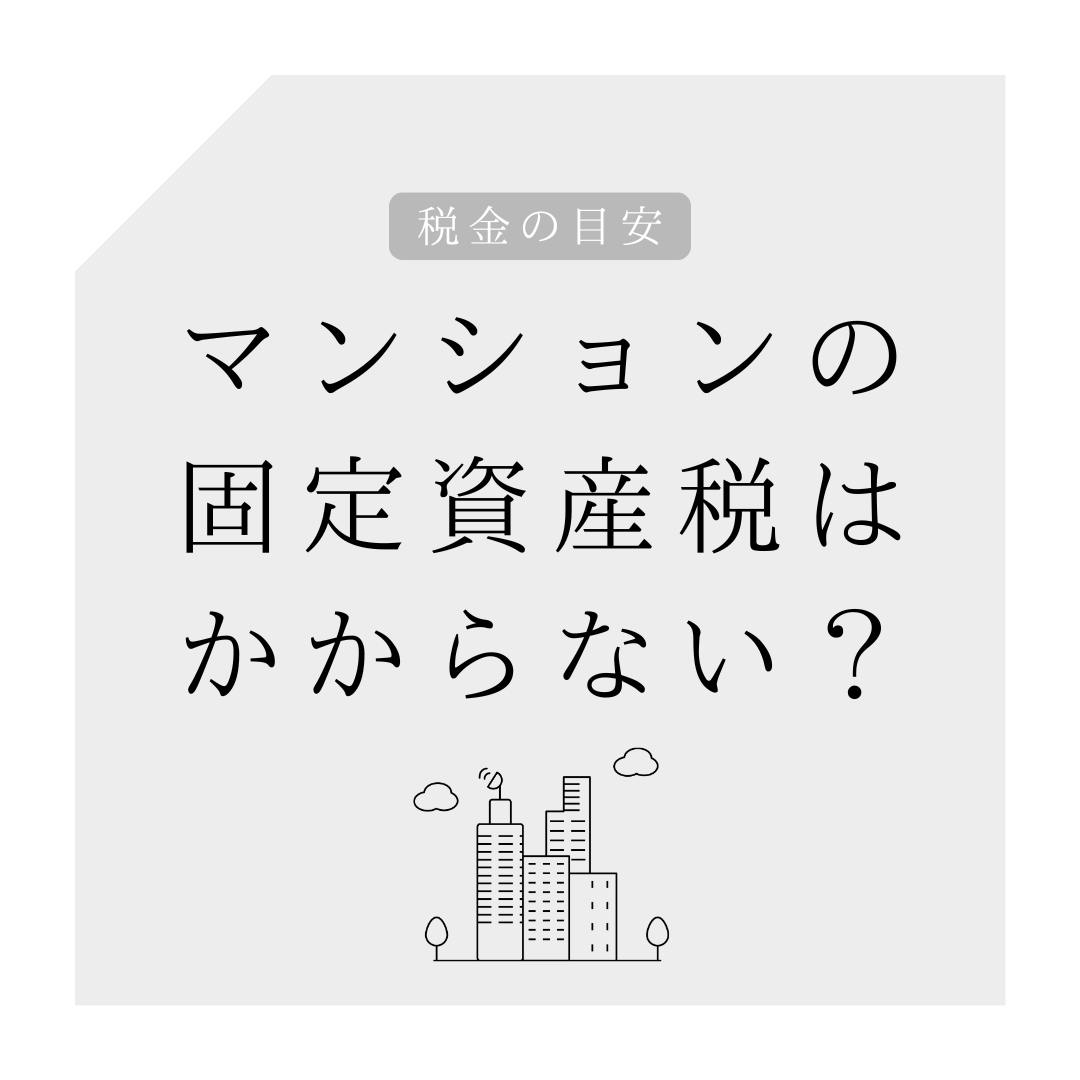
「マンションは土地を共有しているから、固定資産税がかからない」
──そんな話を耳にしたことはありませんか?
実はそれ、半分は誤解です。
マンションでも戸建てと同じように、土地と建物の両方に固定資産税がかかります。
ただし、「土地が共有」「建物が鉄筋コンクリート造」という点で、
戸建てよりも税額が抑えられるケースが多いのも事実です。
この記事では、マンションの固定資産税の仕組みや計算方法、
そして戸建て・賃貸とのコスト比較まで、わかりやすく解説します。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課される税金です。
市区町村が資産評価額をもとに計算し、毎年5〜6月ごろに納税通知書が届きます。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
評価額は、購入価格の約70%程度が目安。
例えば、3,000万円の住宅なら評価額は2,100万円前後になります。
マンションは「建物部分」と「土地部分」に分かれて課税されます。
マンション全体の評価額を、それぞれの専有面積割合で按分。
鉄筋コンクリート造(RC造)のため耐用年数が長く、評価額の下落も緩やかです。
マンション全体の敷地を、各住戸の持分比率で按分します。
1棟全体で1000㎡の土地があり、1戸の持分が2%であれば、
その2%分にだけ固定資産税が課税される仕組みです。
そのため、同じ立地でも土地を単独で所有する戸建てよりも負担が小さいのが一般的です。
たとえば、新築マンション(専有面積70㎡・土地持分40㎡)を購入した場合の試算です。
| 項目 | 評価額の目安 | 税率 | 年間税額 |
|---|---|---|---|
| 建物部分 | 約2,000万円 | 1.4% | 約28,000円 |
| 土地部分 | 約1,000万円(持分換算) | 1.4% | 約14,000円 |
| 合計 | ー | ー | 約42,000円/年 |
実際の税額は自治体や評価額によって異なりますが、
新築マンションなら年間4〜6万円前後が一般的な目安です。
また、新築住宅には「固定資産税の軽減措置」があり、
3年間(マンションの場合は5年間)は建物部分が1/2に減額されます。
この期間中は実質2〜3万円台の負担で済むこともあります。
では、戸建てと比べるとどうでしょうか?
| 種別 | 評価額の特徴 | 年間の固定資産税の目安 |
|---|---|---|
| マンション | 土地が共有で持分が小さいため低め | 4〜6万円前後 |
| 戸建て住宅 | 土地を単独所有、建物も木造で評価額が下がりやすい | 6〜10万円前後 |
マンションは土地を共有している分、土地にかかる税負担は少ないですが、
その一方で「管理費」「修繕積立金」「駐車場代」が毎月発生します。
長期的に見ると、“固定資産税が安い=維持費が安い”とは限らない点に注意が必要です。
賃貸住宅の場合、固定資産税はオーナーが負担します。
そのため「税金がかからない」と思いがちですが、
実際には家賃の中に固定資産税分が含まれていると考えられます。
つまり、毎月家賃を支払っている限り、
自分の資産にはならないまま”間接的に税金を払い続けている”のと同じ構造です。
固定資産税は『3年に一度見直し(評価替え)』が行われます。
また、築年数が経過するごとに建物の評価額が下がるため、
築10年で約20〜30%、築20年で約50%前後まで下がることもあります。
ただし、都心部や駅近など地価の高いエリアでは、
土地の評価額が下がりにくいため、トータルの税負担は大きく変わらない場合もあります。
浜松・静岡エリアのように地価が比較的安定している地域では、
評価額の変動が少なく、税負担を長期的に見通しやすいというメリットがあります。
固定資産税はあくまで住宅コストの一部です。
マンションには管理費・修繕費・駐車場代などの”隠れ維持費”がかかるため、
月々の負担を合計すると戸建てと大きく変わらないこともあります。
例えば──
このように、「税金は安くても維持費は高い」のがマンションの特徴です。
逆に戸建ては、固定資産税こそやや高いものの、支払いの内訳がシンプルで自由度が高い点が大きな利点です。
マンションでも固定資産税はかかります。
ただし土地持分が小さいため負担は軽く、初期の税額は比較的安い傾向にあります。
しかし、長期的には管理費・修繕費・駐車場代といったランニングコストが積み重なります。
一方で、戸建て住宅は税金の負担こそやや大きいものの、
といった“暮らしの自由度”が魅力です。
地価が安定している浜松・静岡エリアでは、
同じ予算でも土地付き注文住宅を建てる選択肢が現実的です。
PG HOUSEでは、ZEH水準を標準仕様とした「高性能 × コストパフォーマンス」の家づくりを提案しています。
固定資産税だけでなく、光熱費や修繕費も含めた“総コストを抑える設計”が可能です。
固定資産税を気にするよりも、
「長く安心して暮らせる家」を持つことが、最終的に一番の節約です。